未来につながる大きな出会い。憧れた作業療法士の存在
作業療法士を目指したのは高校3年生の春。野球部の練習中に足首の靭帯を損傷し、手術を受け、ギブスが取れるまで1ヶ月半に渡る入院を余儀なくされた。それは17歳の若者にとってとてつもなく長い時間だった。
「野球を続けることができないかもしれない」
そんな傷心の最中、療法士と懸命にリハビリに取り組んだ。テスト期間中は看護師が勉強できる環境を整え、辞書を片手に勉強を教えてくれた。セラピストや看護師と過ごした時間は、精神的な支えとなった。
それまで医療という選択肢がなかった浅倉は、そのときから医療現場に憧れを抱き、その道を目指す。高校卒業後は「大分リハビリテーション専門学校」で3年間、作業療法士の知識や技術を学んだ。
専門学校3年の時、10週間の長期実習に挑んだ浅倉は、人生に大きく関わる出会いに恵まれた。それは大分中村病院で作業療法士(OTR)として活躍していたリハビリ部長(当時)の古原岳雄。良い師との出会いは、浅倉の人生において偶然であり、必然だった。古原OTRと専門学校時代の先輩のもと、熱心に指導を受けた。

「患者はどういう心理状態で入院しているか」
「今の患者の言葉をどう受け止めるか」
「治療の環境が患者に及ぼす影響をどう考えるか」
まだ新人の浅倉に古原は常に質問を投げかけ、自ら答えを導けるように考えさせる機会を与えた。「古原部長の考えも織り交ぜながら話してくれますし、考えさせてくれる時間が結構ありました」。
浅倉は古原のもとで働き、治療理論・技術だけでなく、患者との向き合い方をもっと学びたいと大分中村病院への就職を決めた。

右も左もわからぬまま、回復期病棟の立ち上げに携わる
2000年、浅倉は大分中村病院に就職。当時の理学・作業療法士(セラピスト)は古原と浅倉含め、わずか5人。リハビリを実施する際は、一般病棟の病室からリハビリテーション室まで看護助手が行う状況だった。当時は日常の生活を病棟で訓練するという視点は今よりも少なかったという。
その年の6月、浅倉は回復期リハビリテーションの病棟の立ち上げに携わる。「何が正解かわからない」という手探りの状態からスタート。訓練室でのリハビリに集中していた状況をどのように改善していくかが大きな課題だった。七森医師(現在院長)と直接議論を重ね、プロジェクトの一員として懸命に取り組んだ。
移行した後は、病床も増え、日常生活動作(ADL)の向上のため、訓練の一環として送迎を担当療法士が行ったり、新たなプログラムに取り組むなど、効率的かつ、良質なリハビリテーションの提供や在宅復帰の支援が可能となった。
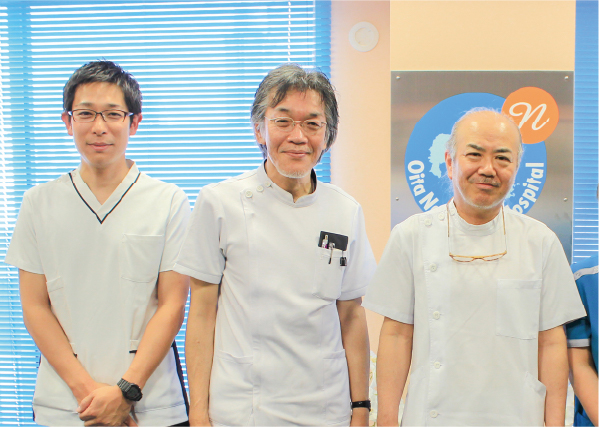
当時の写真 中央=古原、右=七森(2020年撮影)
回復期から退院後の家屋調査も推進した。家屋調査は回復期の患者の自宅や周辺環境を詳細に調査し、退院後に自宅で安全に過ごせるかを判断するものだ。玄関・寝室・トイレ・風呂の動線、家族のサポート体制など実際に確認し、自宅への復帰が現実的なのかどうかを事前に知ることで、患者とその家族に安心を与えられる。
それまでは家屋状況がわかる写真と設計図などデータだけで模擬的に対応していたが、家屋調査ができる体制を整えたことで、退院後の生活支援がよりスムーズにできるようになった。現在も患者の在宅復帰を目指して、担当療法士、医師、看護師、地域のケアマネージャーたちと連携し、家屋調査を実践している。
移行に伴い、新たなプログラムにもたくさん取り組んだ。印象に残っているのは、複数名で取り組む集団リハビリ。集団での活動は患者に社交的な場を提供することができ、他の患者とコミュニケーションを通じて、潜在的な能力を発揮することもあるという。
病棟生活だけでは見えない患者の新たな一面を看護師が気づき、今後の治療に活かすこともできる。数年前コロナ禍で集団での活動自粛が求められ、現在集団リハは行っていないが、将来的には、また復活させたいと浅倉は考えている。

24時間365日体制でよりよい医療の提供に挑む
その後、たくさんの現場経験を積んだ浅倉は、急性期病棟での臨床を経験し、土日・祝日にストップしていたリハビリの実施とチーム医療の重要性を実感。他職種と連携し、患者が入院生活の中で回復できるように努める365日リハビリを提供できる体制を目指した。
「1日24時間のうち、療法士が患者さんに接する時間は1日最大3時間です。残りの時間は医師、看護師、看護助手、薬剤師などそれぞれの専門家による時間。なので他職種と連携しないと、患者さんの24時間の状態を把握できない。土日にもリハビリを実施することで、患者さんのよりよい回復につながります」
2017年、浅倉は一般病棟・回復期リハビリテーション病棟の24時間365日体制の構築という大きなプロジェクトに挑む。しかし、いざ始まると、組織が大きくなることによって困難になる情報共有の促進、人材育成、土日のリハビリ実施によるリスクなど、課題は山積み。
「土日のリハビリ実施が患者の回復にこれだけ有効なんだ、とデータを持って医師に伝えたりしましたね」ひとつひとつ課題をクリアにしながら、1年ほどかけて体制を整えた。
現在、リハビリテーション部では、100人ほどセラピスト(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が在籍し、平日は常時60〜70人ほど動いている。24時間365日患者をサポートできる体制を整え、他職種と連携し、その人らしい生活を再び取り戻せるように社会・在宅復帰を目指し、退院を支援している。


心を動かすか、体を動かすか。1日ひとつできればいい。
様々な組織改善の大きなプロジェクトに携わる間も、現場で作業療法士としてリハビリを実践し、古原から多くを学んだ。その中で強く印象に残っているのは人と人の向き合い方。
人は言葉と表情が矛盾していると、違和感がある。だから、患者の言葉と表情から真の心を読み取るように意識する。意思疎通が困難な患者には声をかけて、肌に優しく触れる。
「日頃から優しく患者さんと向き合えるようにしなさい、と言われていました。“優しく”というのは、押し付けの優しさではなくて。どんな状況でも自分が優しくできる心構えが大事と教わりました」
だから、どんなときも笑顔を忘れない。“表情で人を包み込むこと”は古原が実践していたことだ。それは、今も患者や職員に対するコミュニケーションの柱となっている。
それでも大変な時、思い出すのは、心に刻まれた古原の言葉。
「患者さんの心を動かすか、体を動かすか、どっちか。どっちもできんかったら、どっちかでいいんよ。どっちもできたら最高」。多くの壁を乗り越えてきたからこそ、なお心に響く。
そんな浅倉は作業療法士として患者に寄り添い、どうすればできるかを一緒に考える。
「患者さんが自分の役割ややりがいを見出したときや、何かを達成した瞬間が一番嬉しいんですよね。歩くことで誰かに会うとか、そこに行って何かを作るとか、歩く・座ることによって、何か1つできると嬉しい。その土台を作ってくれるのは理学療法士で、自分1人では全部できない。歩いた先に何があるかっていうのをちゃんと考えるのは、僕たちの役割だなと思っています」

職員のメンタルヘルスにも注力。健康経営を目指して
浅倉は今リハビリテーション部の部長として、多くのスタッフの生産性向上や安全管理の仕組みづくりなど、部全体のマネジメントを担っている。
「自由度が高い大分中村病院は成長につながる環境がある」という。
多くの診療科があり、専門性の高い医師、看護師、コメディカルが在籍し、さまざまな疾患の患者に対応している大分中村病院では、他職種との連携もしやすく、それぞれの意見にもしっかり耳を傾けてくれる土壌があるという。そんな雰囲気の中、自分自身は成長を重ねてきて、今がある。
そんな大分中村病院で20年以上切磋琢磨してきた浅倉がずっと大事にしていることは、「誠実に患者と向き合う。スタッフと向き合う」こと。患者はもちろん、リハビリスタッフ、他職種の職員とできる限り、コミュニケーションをとり、自分自身で考え込みすぎないように意識しているという。患者には合間の時間での声かけを忘れない。
もちろん自分自身に向き合うことも。仕事以外の時間は、自分の時間や家族の時間を大事に過ごす。毎日朝5分の散歩やスポーツなどで外の空気に触れて“五感”を刺激し、自身の仕事につなげている。自身の健康管理も、よりよい医療提供につながっていくためだ。
ここ数年、ストレスや悩みを抱えて体調不良を訴える職員を多く見てきた。「今は何かあったら対処療法しかないんです。だから予防できるように努めたい。職員のメンタルヘルスは病院の経営にも直結します。将来的には健康経営を目指して、今は勉強会に参加したり、自身で調べて学びを深めているところ」
かつての師から学んだように、これまでもこれからも笑顔で患者やスタッフに寄り添い、未来に向けて自身の成長も続いていく。




